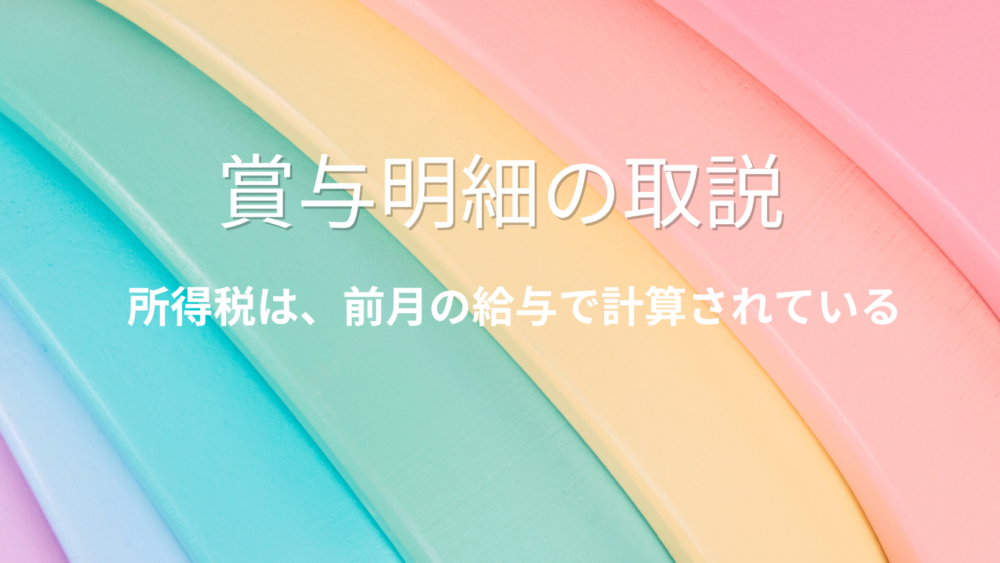賞与の手取りが、どうしてこうなるのかを解明したところ
思わぬ発見がありました。
どれだけ複雑にわかりにくく構成されているか
また、会社に負担してもらっていることもわかりました。
例をつくりましたので、ご自身の金額で計算してみれば納得できるはずです。
東京都の会社に勤めている会社員(扶養なし)で
前月の給料20万円の人が賞与333,333円を受け取った場合を解説していきます。
賞与明細
| 賞与総額(総収入) | 333,333円 |
| ①健康保険 | -16,650円 |
| ②介護保険(40歳以上) | -3,030円 |
| ③厚生年金 | -30,470円 |
| ④雇用保険 | -2,000円 |
| ⑤所得税 | -11,483円 |
| 差引支給額(手取り) | 269,700円 |
賞与総額-①-②-③-④-⑤=差引支給額
①健康保険
健康保険は保険証の発行先に納めます。
大きく分けて2つ。
各種健康保険組合か、協会けんぽです。
ご自身の保険証に記載されている発行先を調べれば保険料率はすぐわかります。
協会けんぽで解説します。
16,650円の算出方法
| 計算の基となる数字 | 333,000円(千円未満切捨て) |
| 保険料率 | 10% |
333,000円×10%=33,300円
事業主と本人で折半します。
33,300÷2=16,650円
| 事業主負担 | 16,650円 |
| 本人負担 | 16,650円 |
②介護保険(40歳以上)
介護保険も納め先は健康保険と同じです。
なので、協会けんぽになります。
3,030円の算出方法
| 計算の基礎となる数字 | 333,000円(千円未満切捨て) |
| 保険料率 | 1.82% |
333,000円×1.82%=6,060円
事業主と本人で折半します。
6,060÷2=3,030円
| 事業主負担 | 3,030円 |
| 本人負担 | 3,030円 |
③厚生年金
厚生年金は公的年金なので、保険料率は一律です。
納め先は日本年金機構です。
30,470円の算出方法
| 計算の基礎となる数字 | 333,000円(千円未満切捨て) |
| 保険料率 | 18.3% |
333,000円×18.3%=60,940円
事業主と本人で折半します。
60,940÷2=30,470円
| 事業主負担 | 30,470円 |
| 本人負担 | 30,470円 |
④雇用保険
雇用保険は公的保険なので、保険料率は一律です。
2,000円の算出方法
| 計算の基礎となる数字 | 333,333円 |
| 保険料率(本人負担) | 0.6%(6/1000) |
| 保険料率(事業主負担) | 0.95%(9.5/1000) |
雇用保険は賞与総額で計算します。
保険料率も折半ではありません。
本人負担は、333,333円×0.6%=2,000円
事業主負担は、333,333円×0.95%=3,166円
※会社のほうが多く負担してくれます。
⑤所得税
前月の給与で税率が決まります。
正確に言うと、前月の給与総額から社会保険料が控除された金額です。
前月給与総額-健康保険-介護保険-厚生年金-雇用保険=計算の基礎となる数字
11,483円の算出方法
例は扶養なしです。
扶養人数によって、税率は変わります。
| 賞与所得税率 | 給与-社会保険料控除額 |
| 0% | 68,000円 未満 |
| 2.042% | 68,000円 以上 79,000円未満 |
| 4.084%(該当!) | 79,000円 以上 252,000円未満 |
| 6.126% | 252,000円 以上 300,000円未満 |
| 8.168% | 300,000円 以上 334,000円未満 |
| 10.210% | 334,000円 以上 363,000円未満 |
| 12.252% | 363,000円 以上 395,000円未満 |
| 14.294% | 395,000円 以上 426,000円未満 |
| 16.336% | 426,000円 以上 520,000円未満 |
| 18.378% | 520,000円 以上 601,000円未満 |
| ・ | ・ |
| 41.861% | 2,621,000円 以上 3,495,000円未満 |
| 45.945% | 3,495,000円以上 |
例は、前月の給与20万円ですので 税率4.084%に該当します。
| 計算の基礎となる数字 | 賞与総額-社会保険料控除額 333,333-16,650-3,030-30,470-2,000 =281,183 |
| 所得税率 | 4.084% |
281,183円×4.084%=11,483円
まとめ
いつからこの計算方法になったのかは不明ですが
令和5年12月時点では、上記の率で合っています。
裏付けとして、全ての率の公表先をリンクしました。
例の会社員の層が厚いのは
所得税からもお察しいただけるのではないでしょうか。
そしてまた、稼ぐ人の税率はとんでもなく高いです。
3,495,000円以上の人の税率45.945%を計算してみると
所得税だけで1,605,777円です。
3,495,000円(社会保険料控除後)-所得税1,605,777円=1,889,223円
手取りは半分以下が予想されます。
このように理解してみると
私は世の中の見方が変わった気がしています。
読んでいただきありがとうございました